その他私のホビー
2025年2月 中村 淳 (第24代・昭和56年卒)
[記事番号:c0153]
雑感:怖いもの見たさ その2 (資料:無し
)
今のところ,自分はひどく不幸でもなく,そこそこ幸せに暮らせている.そんなとき,現実になってほしくないが,自分に起こる恐怖の事態を想像することがある.
恐怖といえば,小学校にあがる前に観ていた「恐怖のミイラ」というテレビ番組を,最近YouTubeで観た.怖いのに,夜中にトイレに行けなくなるのに,観ることをやめられないのだ.しかしその怖い番組も今はエンターテインメントに見えてしまう.ここで書こうとしているのは,そういうモンスターや怪談のような荒唐無稽な話*のことではない.もっとリアリティーのある,大人にとっての怖い話だ.
* とはいえ,洋の東西を問わず,評価の高い怪談やミステリーは多くある.自分はそれらを読むことも好きだ.
人間,やっぱり死ぬことは怖い.自分が物理的に死ぬこと,または実質的に死ぬこと,あるいは社会的に死ぬこと.これらに恐怖する一方で,その情況はどんなだろうとあれこれ思いめぐらせてしまうのは,おそらく自分だけではないだろう.
死ぬという究極状態の前段階は,通常,老いることだ.これも恐ろしい.恐ろしいが,これは死ぬことよりももっと現実として受け入れなければならない.おそらく自分はいま人生の時間軸の75%あたりにいるはずだ.老いには肉体の老いと,精神の老いがある.前者は人生のかなり早い時期から,中年以後でははっきりと現れるから,恐れるというより,うまく付き合うべき対象と考えている.しかし後者はなかなか認めたくない.
自分の肉体的,精神的状態が衰えること以外に,年齢とともに時間の進みがどんどん速くなり,「時間切れ」が近づいてくるという漠然とした恐怖もある.精神の老いはこの「時間切れ」の恐怖を緩和する効果があるのかもしれない.つまり精神の老いは防衛的な現象なのかもしれない.
歳をとると,個人差はあるが,仕事に追われることが少なくなる.その分のんびりするのかといえば,自分の場合,むしろ仕事に積極的になったり,趣味に打ち込んだりする.生きがいとか,自己の充実などという言い方もできるが,「何かやっていないと,あっという間に歳をとりそうだから」という思いもある.
「その1」で触れた「サナトリウム文学」の代表作は,世界的にはトーマス マンの「魔の山」だろう.サナトリウム文学には悲劇的なストーリーが多いが,「魔の山」はむしろ思索的である.その主人公がスイスのサナトリウムを訪れた当初の記述に以下のような文章がある.そしてこの文章の内容は,著者がこの小説(といっても大作だが)で描きたかったテーマの1つだと思う.少し長いが引用する.
「退屈ということの本質について,いろいろとまちがった考え方が広まっている.生活の内容が興味のある新奇なものであれば,それは時間を‘追い払う’,つまり短くしてくれるが,単調や空虚は時間の歩みに重しをかけて遅くするものだ,と一般に信じられている.これは無条件に正しいとはいえない.
「空虚や単調は,瞬間とか1時間とかいう時間ならば,それを伸ばして退屈なものにするだろうが,大きな,非常に大きな時間量になると,それを短くして無に等しいもののように消え失せさせる.その逆に豊富で興味のある出来事は,1時間や1日くらいならば,それを短くし飛ぶように過ぎ去らせてしまうこともあるが,しかし時間が大量になると,時間の歩みに幅と重みと厚みを与えるから,事件の多い歳月は,風に吹き飛ばされてしまうような貧弱で空虚で重みのない歳月よりも,はるかにゆっくりと経過するものだ.
「いわゆる退屈さとは,実は単調な状態の結果として時間が病的に短くなることだ.同じことが延々と続くことによって大きな時間量が収縮し,いずれは心が動揺し死への恐怖に襲われる.1日が他のすべての日と同じなら,多くの日々も1日と同じことである.毎日がまったく同じならば,どんなに長い人生も非常に短いものに,まるで一瞬のうちに過ぎ去ってしまうように感じられるだろう」
この文章を読んだとき,1970年代のブリティッシュ ロックの曲,ピンク フロイドの「タイム」が思い浮かんだ.冒頭にたくさんの目覚まし時計がけたたましく鳴る,有名な曲だ:
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run and you run to catch up with the sun but it's sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way but you're older
Shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
時計が時を刻み,退屈な1日が過ぎていく
おまえは無雑作に時を浪費する
故郷のちっぽけな土地から出ようともせず
何をすべきか,誰かや何かが教えてくれるのを待つだけ
陽だまりの中で寝そべるのにも飽きて,家の中から雨を眺める日々
おまえは若く人生は長い,無為に潰す時間はいくらでもある
そしてある日,おまえは10年が過ぎ去ったことに気づく
いつ走りだすべきか誰も教えてくれず,出発の合図を見逃したのだ
太陽に追いつこうとおまえはひた走る,しかし太陽は沈んでいく
追い続けると太陽はおまえの背後から再び姿を現す
くらべてみれば,太陽は変わらないのにおまえは老いていく
息切れは激しくなり,また1日死に近づく
歳月は年ごとに急ぎ足で過ぎ去り,息をつく暇もない
企ては水泡に帰すか,数行のなぐり書きのまま終わる
英国人らしく,おまえは静かな絶望に身をゆだねていく
1960–70年代のロック ミュージックには反ベトナム戦争や階級社会批判を訴えるメッセージ的な曲が少なくないが,こんな絶望的な内容の歌詞を自分は聴いたことがなかった.デヴィッド ギルモアの泣きのギターはもちろん素晴らしい.それに加えてベーシストのロジャー ウォーターズによるこの暗い歌詞が強いインパクトを与える.おそらくウォーターズはオリジナル メンバーのシド バレットが数年前に精神を病んで脱退したショックを歌詞の形にしたのだろう.
暗い歌詞といえば,「その1」の冒頭に書いた森田 童子の多くの曲もそうだ.ただし「タイム」のような他者に対する教訓的,警告的なものではなく,自分の悲劇的な状況をむしろかみしめるようなものが多い.いかにも日本的だと思う.静かな絶望に身をゆだねるのは英国人だけではない.
我ながら話の一貫性が乏しいと思うが,要するに自分が言いたいことはこういうことだ:「怖いもの」とは,自分の「時間切れ」がくるまでのカウント ダウンをしながら,持ち時間が少しずつ減っていくという焦燥感が最初はゆっくり,いずれはすごい勢いで高まるだろう状況のことだ.人生であれ何であれ,計画したことの多くは期待したペースで成果が出ない.時計やカレンダーを見ると,残り時間がどんどん減っている.もっと周到な計画を立てて着実に進めればよかったのにと後悔するときの,じりじりするような,いてもたってもいられない,あの感じだ.自分の成果を批判的に評価する人には,多かれ少なかれ,この感覚がわかってもらえると思う.
最後に多少前向きなことを書く.自分に限らず,人にはものごとをネガティブに捉えるときとポジティブに捉えるときとが周期的にやってくる.恐怖の状況,不安な状況をときどき想像するのは,ひょっとすると,自分がそこそこ幸せであるということをより強く感じるためのスパイスなのかもしれないとも思う.

|
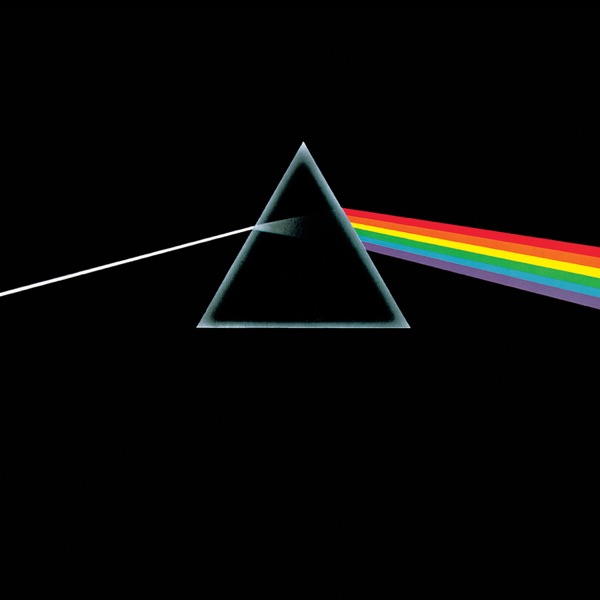
|
| トーマス マン「魔の山」の舞台であるダヴォス,スイス 出典:Wikimedia Commons | ピンク フロイド「タイム」が含まれるアルバム「狂気」 |
コメント
以下の「投稿」ボタンをクリックし、表示される画面に必要事項をご記入の上投稿下さい。 なお、内容のチェックをさせていただきますから、公開までに多少のお時間をいただきます。

